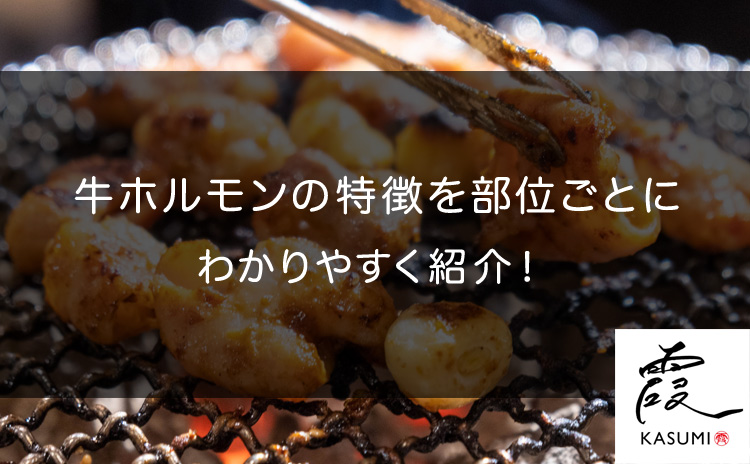今日ではポピュラーな食材となっているホルモン。
油が多く、味が濃いと思われがちなホルモンですが、実際は赤身に比べてカロリー低いことから女性や、ダイエット中の人にも人気があります。
赤身より好きという人も多いホルモンですが、様々な種類があり、部位によってどのような味わいなのかも気になるところです。
この記事では、代表的なホルモンの特徴とおいしい食べ方を紹介します。
ホルモンとは
ホルモンとは主に内臓肉のことを指しますが、ホルモンという名称で呼ばれるようになったのは諸説あります。
有名な説で、大阪弁で「ほるもん(捨てるもの)」という言葉から、もともと捨てていたけど食べるようになったというものがありますがこれは俗説とされています。
公益社団法人 日本食肉協議会が発行した「畜産副生物の知識」によると次のように説明されています。
【ホルモンの語源】
ホルモンの語源は、大阪弁の「捨てるものを意味する『放るもん』」説や、医学用語であるドイツ語のHormon(ホルモン)、英語のhormoneは、動物体内の組織や器官の活動を調節する生理的物質の総称から、栄養豊富な内臓を食べると、活力がつくとして名付けられた説など諸説あります。
ホルモン料理の名称は戦前から存在し、戦前においては、内臓料理に限らず、スタミナ料理一般、例えば、スッポン料理などもホルモン料理と呼ばれていたことから、ホルモンは「放るもん」ではなく、明治維新のころの西洋医学(主にドイツ)の影響を受け、栄養豊富で活力がつくとして名付けられたものと思われます。
引用:「畜産副生物の知識」発行元 公益社団法人 日本食肉協議会
ドイツ語の医学用語である「ホルモン」という言葉からみんなが使うようになったというのが通説のようです。
牛肉のホルモンを部位ごとに紹介
では実際にどのような名前で、どのあたりの部位のものがあるのかについて解説していきましょう。
ここでは焼肉店で目にすることの多いポピュラーなホルモンの部位の特徴を紹介していきます。
タン
焼肉の定番のタンは、舌のこと。
脂が少なくあっさりしており、たんぱく質やビタミン、タウリンも含まれているのでダイエットや美容、疲労回復も期待できます。
赤身肉のように思われるタンも実はホルモンに分類されます。
ただしこれはお肉を扱うお店において肉の部位を分類するうえで慣例としてホルモンに分類しているということであり、医学的に「タン」=「内臓」ということではありません。
タンは「タン先・タン中・タン元・タン下」と4種類の部位に分けることができ、一般的に焼肉で提供されるのはタン中、タン元です。
特に根元から3~4cmのタン元はタン中に比べて運動量が少なく柔らかでジューシーな味わいとなっています。
タン先、タン下は硬い肉質のため、煮込み料理に使われます。
タンは1頭から取れる量が少なく、人気が高い部位なので、焼肉店やスーパーに並ぶタンはほとんどが輸入品となっています。
国産黒毛和牛のタンは流通が極端に少ないので、もしお店で見かけた際はぜひ注文しましょう。
ツラミ
ツラミとはほほ肉のこと。
一頭からだいたい1㎏しか取れない希少な部位です。
よく動かす部分のため肉質は硬く、焼肉店では薄切りで提供されることが多い部位です。
ゼラチン質、タンパク質が多く含まれていて、噛めば噛むほどお肉の旨味を感じることができます。
煮込むことで口の中でほどけるような柔らかさになるので、ホロホロになるまで煮込んだ「牛ホホ肉の赤ワイン煮込み」などの煮込み料理も人気です。
ウルテ
のどにある気管の軟骨をウルテといいます。
フエガラミという呼び方もあります。
一頭から500gしかとれない希少な部位で、淡白な味わいでコリコリとした触感が人気です。
ハツ(ココロ、ハート)
ハツやココロ、ハートと呼ばれる部位は心臓のこと。
鉄分、ビタミンも豊富で免疫力や疲労回復、美容効果も期待できます。
クセは少なく、あっさりした味わいが特徴で、ホルモンは苦手という方にもおすすめの部位です。
ミノ
牛には4つの胃がありますが、そのうち、第一胃の部分をミノといいます。
厚みがあり歯ごたえの良い部位で、とくに厚みのある部位は脂を含んでおり、その見た目からミノサンドとも呼ばれます。
味やニオイのクセは少な目で食べやすいホルモンです。
ハチノス
見た目が蜂の巣に見えることからこの名がついたハチノスは胃袋の第二胃の部分になります。
ハチノスは一頭から1㎏ほどしかとれない希少な部位です。
匂いの強い部位で、美味しく食べるためには、丁寧に黒い皮を剥がすなど、根気のいる下処理が必要です。
食べ方は焼肉のほか、もつ鍋や煮込み料理によく使われます。
イタリアでは胃袋をトリッパとよび、ハチノスをトマトと煮込んだ料理が定番です。
センマイ
4つある胃袋の第三胃の部分をセンマイといいます。
胃のひだがたくさん重なっていることから千枚(センマイ)という名がつきました。
すこしグロテスクな見た目ですが、クセのないあっさりとした味わいでコリコリとした触感を楽しめる部位です。
焼肉のほか、韓国で「チョジャン」と呼ばれるタレといっしょに刺し身で食べるのが定番です。
アカセン(アカセンマイ、ギアラ)
4つある胃袋の第四胃の部分をアカセン(ギアラ)といいます。
脂が多く、噛むほどに旨味が感じられ、コリコリとした歯ごたえがホルモン好きに人気の部位です。
焦がさないように注意しながらもしっかり焼くことで身が柔らかくなり美味しくいただけます。
サガリ
横隔膜についている筋肉部のうち腰椎側をサガリといいます。
一頭から1本しかとれない希少な部位です。
肉質は柔らかく、適度に脂も含まれることから人気があります。
また赤身肉に近く、カロリーも少ないのでヘルシーにお肉を食べたい人にはおすすめです。
ハラミ
横隔膜についている筋肉部のうち肋骨側をハラミといいます。
こちらも肉質は柔らかく、適度に脂も含まれることから焼き肉で人気のある部位です。
サガリと同じ横隔膜周りのお肉ですが、ハラミの方が脂は多めです。
和牛のハラミは流通が極端に少なく、スーパーや焼肉店で見かけるハラミは外国産である場合がほとんどです。
内臓肉のため、鮮度や処理によっては臭みがでますが、丁寧に処理された新鮮な和牛のハラミは、あっさりしていて柔らかく、肉の旨味が強く感じられる部位なので、一度は味わってもらいたい部位です。
レバー
肝臓の部分をレバーといいます。
食感や味に特徴があるので苦手な方も多いですが、とても栄養価の高い部位です。
高たんぱく、低カロリー、鉄分、ビタミンなど、その高い栄養価から「栄養の宝庫」と言われることも。
臭みのあるイメージですが、しっかりと下処理を施した新鮮なレバーは臭みも少なく歯ごたえもよく食べやすいです。
以前までレバ刺しとして生でも食べられていましたが、篤な食中毒の原因となる腸管出血性大腸菌が検出されることがあるため、2012年の食品衛生法に基づく規格基準の改正により、生食用として牛のレバー(肝臓)の販売・提供が禁止となりました、
コプチャン(ヒモ・ホソ・マルチョウ)
小腸の部分をコプチャンといいます。
関西ではヒモ、ホソとも呼ばれていて、「ホルモン」としてメニューに記載している焼肉店もあるようです。
開かずに筒のままの提供される場合はマルチョウと呼ばれます。
一頭から約40mほど取れるため安いうえ、脂ものっていてコラーゲンやタンパク質も多いため人気の部位です。
焼肉はもちろん、もつ鍋やもつ炒めなど多くの料理で使われています。
シマチョウ(テッチャン)
大腸の部分をシマチョウといいます。
関西ではテッチャンと呼ばれます。
下処理が難しく大変なので「シマチョウが美味しいお店は他のメニューもおいしい」と言われるほど。
しっかりとした歯ごたえと旨味が詰まったシマチョウはファンも多いです。
いろんなホルモンを食べてみよう
ホルモンは沢山の種類が有り、今回紹介した部位以外にもまだまだ希少部位がありますが、それぞれに全く違った食感や味わいが楽しめる部位です。
内臓というだけで敬遠してきた人も、きっと好きなホルモンの部位があると思います。
是非この記事を参考にいろいろなホルモンを食べてみてくださいね。